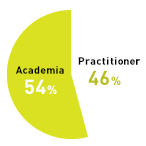|
第16回価値共創型マーケティング研究報告会レポート「価値共創のメカニズムと実践的アプローチからの示唆」 |
第16回 価値共創型マーケティング研究報告会 > 研究会の詳細はこちら
テーマ:「価値共創のメカニズムと実践的アプローチからの示唆」
日 程:2016年12月18日(日)13:30-16:30
場 所:大阪産業大学 梅田サテライトキャンパス
【報告会レポート】
第16回目の研究会では、価値共創を促進する実践的アプローチについて検討いたします。株式会社電通の宮脇氏は現在脚光を浴びている「カタリスト」に注目することで、主体間の意志や能力がどのように作用すれば価値が共創され、促進されるのかについて分析されました。この最新の研究成果をご披露いただきました。
報告者と内容は以下の通りです。
「価値共創マーケティングの理論と実践」
村松 潤一 氏(広島大学大学院 社会科学研究科 教授)
 村松先生は、最初に、企業が価値創造を担うとした20世紀型のマーケティング観をあらためるのが、S-Dロジック登場以降のマーケティング研究であることを確認されました。新しいマーケティングの領域は、顧客の消費プロセスにあるといえます。また、価値創造者たる顧客の消費プロセスに入り込むことによって、価値共創が可能になると考えられます。このような考えに基づき、新たな研究課題(①消費プロセスにおける顧客の消費行動, ②企業と顧客との共創プロセス, ③顧客の消費プロセスで行うマーケティング, 共創される文脈価値)を設定することができ、価値共創マーケティングのアプローチとして、4C(Contact, Communication, Co-Creation, Value-in-Context)の視点が有効ではないかと主張されました。さいごに、今日の社会において、すべての企業はサービス企業であるといえ、それはすなわち、顧客の生活世界における文脈価値の中で機能することにほかならないといえます。このようなマーケティングを検討していこうとするのが、本研究会のねらいであります。こうした価値共創マーケティングの概要をお示しになりました。
村松先生は、最初に、企業が価値創造を担うとした20世紀型のマーケティング観をあらためるのが、S-Dロジック登場以降のマーケティング研究であることを確認されました。新しいマーケティングの領域は、顧客の消費プロセスにあるといえます。また、価値創造者たる顧客の消費プロセスに入り込むことによって、価値共創が可能になると考えられます。このような考えに基づき、新たな研究課題(①消費プロセスにおける顧客の消費行動, ②企業と顧客との共創プロセス, ③顧客の消費プロセスで行うマーケティング, 共創される文脈価値)を設定することができ、価値共創マーケティングのアプローチとして、4C(Contact, Communication, Co-Creation, Value-in-Context)の視点が有効ではないかと主張されました。さいごに、今日の社会において、すべての企業はサービス企業であるといえ、それはすなわち、顧客の生活世界における文脈価値の中で機能することにほかならないといえます。このようなマーケティングを検討していこうとするのが、本研究会のねらいであります。こうした価値共創マーケティングの概要をお示しになりました。
「エージェントからカタリストへ -価値共創における触媒機能の可能性-」
宮脇 靖典 氏(株式会社電通 ビジネス統括局 次長)
 宮脇先生は、価値共創の領域の拡大や活性化について研究されました。これは、広告代理店のようなエージェント企業が、企業特性によって生じる課題を克服するための視点として必要なものです。今回は、カタリスト(触媒)が機能することで、分野横断的な共同事業を成功に導いたり、あるいは、創造的な衝突を促進させることで、新たな次元の実践を導くことができるのではないかという仮説に基づき、実証研究を展開しました。
宮脇先生は、価値共創の領域の拡大や活性化について研究されました。これは、広告代理店のようなエージェント企業が、企業特性によって生じる課題を克服するための視点として必要なものです。今回は、カタリスト(触媒)が機能することで、分野横断的な共同事業を成功に導いたり、あるいは、創造的な衝突を促進させることで、新たな次元の実践を導くことができるのではないかという仮説に基づき、実証研究を展開しました。
事例研究の対象は、カタリストを公称する日本の企業・団体のほか、触媒機能がみられる日本の企業・団体とし、触媒機能が求められた背景から実践の成果や課題について考察していきます。すると、価値を共創する主体間の意志・能力のマッチングが問題になります。こうした村松(2015)の主張に加え、コンピタンスに2つの方向(深さと広さ)があると指摘したほか、触媒によって生じた成果の超越性という2つの視点による検討の重要性が示されました。この、触媒機能の評価の分類を試み、その分類に基づいて事例研究に適用し議論を進めていくと、新たな発見が得られました。ただし、その成果は一様でなく、さまざまな解釈とともに可能性を模索することができます。こうした幅広い知見が披露されました。
ディスカッション
宮脇 靖典 氏(株式会社電通 ビジネス統括局 次長)
村松 潤一 氏(広島大学大学院 社会科学研究科 教授)
藤岡 芳郎 氏(大阪産業大学 経営学部 教授)
大阪産業大学 藤岡先生のリードで、本日も参加者全員によるディスカッションが展開されました。
カタリストに関する実証研究には、さまざまな含意がありました。既存の事業を補完すべくカタリストの機能を求める企業・団体もあれば、地域資源の創造や開発を期待する取り組みもありました。予定調和の範疇で取り組みが推進されている場合もあれば、当初想定していた共創の仕組みが機能しないため、方針を変更した企業・団体もありました。中には、共創の仕組みづくりとともに新たな資源の発見が可能になり、その活用が促進され、有機的なつながりを形成させていくといった実績を持つ企業・団体もあります。こうした企業・団体においては、その取り組みを推進する部署がコスト・センターのように揶揄されることなく、組織内において、収益機会の逸失を防ぐうえで重要な場として機能しているとした評価が成立するものもありました。
このような事例分析から明らかなのは、主体間関係の捉えなおしの手続きでカタリストが期待される、あるいは必要とされるようになったといえるかもしれないということです。カタリストが機能することで、間違いなく、社会的背景と接続しながら、何らかの文脈を生成しようとしているのであり文脈創造の契機になっているのかもしれません。
このように考えていくと、従来の経営学(や会計学までも)が、事業活動の時空間における定義が狭いことに気づかされます。このことはすなわち、企業や団体の活動がより大きな社会性あるものへと進展しようとしているのであり、価値共創への注目とその実践が、より大きな視点から、あるいは大胆に主体間関係を描こうとしているのかもしれません。それとともに、主体間関係の検討に必要なのは、何がどの主体に向けて作用し、作用されているのかであります。こうした捉え方を精緻化させ議論することは大変重要であり、その本質的な理解を、参加者全員による質疑から感じることができました。
現象として価値共創を捉えようとしたとき、この現象を重視して新たな局面を構築することが期待されますが、既存の事業活動が直面している課題によって触媒に期待されるゴールが異なるほか、触媒に該当する行為が作用する影響や範囲が多様である場合は、さまざまな解釈が成り立ちます。その可能性は幅広く、成果が大きな意味を持つことは間違いありません。今回もこのことを中心に、活発に質疑が行われましたし、ほかにはない進歩的な議論ができたのではないかと思います。


写真左より、会場の様子、ディスカッションの様子
今回も、長時間に及ぶ研究会にも関わらず、参加者の関心が絶えることはありませんでした。次回の第17回の研究会は、3月5日(日)午後、広島大学東京オフィスにて開催いたします。関心をお持ちの方の多数の参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
文責:今村 一真(茨城大学)